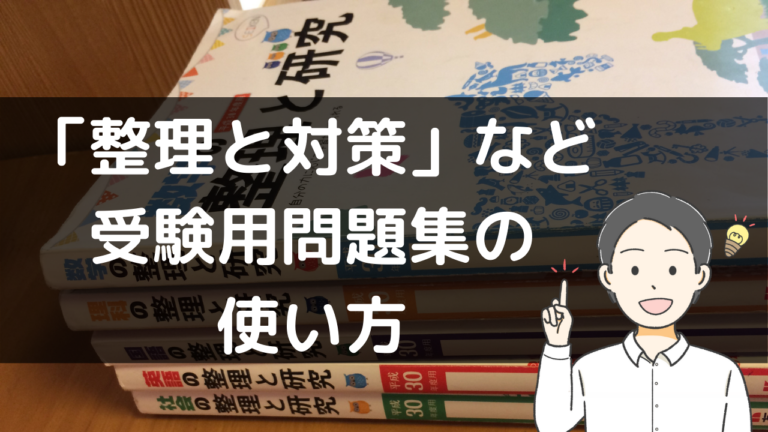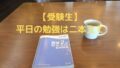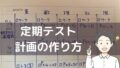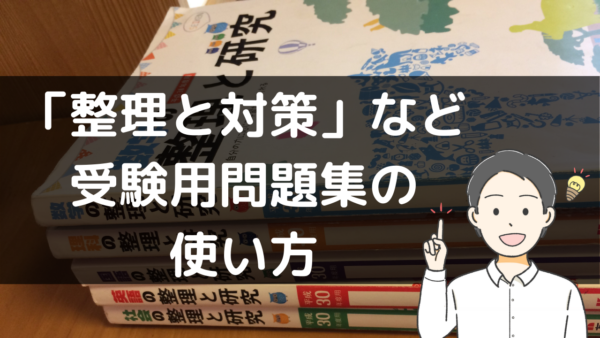
おはようございます。群馬県高崎市の家庭教師、牛込伸幸です。
群馬県では、中学2年生の冬休みに
「整理と対策」「新研究」「整理と研究」
といった受験用問題集が配られる学校が多いです。
この教材、実は
中1〜3の全範囲をまとめて復習できる“超優秀教材”
にもかかわらず、うまく使いこなせていない生徒さんがとても多いと感じます。
そこで今回は、
✔ 中2冬から始める年間活用法
✔ 模試に合わせた使い方
✔ 成績が伸びる「仕上がり基準」
✔ 苦手科目の攻略法
✔ 伸び悩んだときの戻り方
まで、全部まとめて解説します。
①“中2冬休み〜中3になる前”で1周する
この問題集は
・前半→単元別(例:方程式、一次関数)
・後半→実践編
となっています。
中2の冬休みに問題集をもらったら、
前半の「単元別」をまずは3年生になるまでに1周しましょう。
-
毎週末に少しずつ進める
-
理科・社会は忘れていてOK。解説を読みながら進める
-
完璧は目指さず、とにかく「全範囲やり切る」ことが目的
1周目は“慣れるための下準備”です。
この後、模試のたびに同じ範囲を何度も解くので安心してください。
② 中3は「模擬テストの範囲」に合わせて使う
多くの中学では、模試(実力テスト・復習テスト)の範囲が次のように広がっていきます。
-
5月:中1範囲
-
6月:中2範囲
-
7月:中1+中2範囲
-
9月(夏休み明け):中1+中2+中3前半
つまり、問題集もこの流れに合わせて使うのが最適です。
模試にあわせて勉強すると問題集を3周できます。
特に夏休みは徹底的に復習。
使い方のポイント
-
間違えた問題(あいまいな問題含む)に印をつけておく
-
印をつけた問題だけをピンポイントで解きなおす(直後に1回、次回はここを復習してから新しい単元に。解きっぱなしはダメですよ)
-
時間がなければ見直すだけでもOK
この時点では「完璧じゃなくても全然OK」
夏休みや秋以降に何度も回すので大丈夫です。
③ 夏休みまでに“単元別ページの前半”を仕上げる
夏休みが最初の大きな山場。
夏休みが終わるまでに、
✔ 前半の“単元別ページ”を仕上げる
(まとめ → A問題 → B問題まで)
これをひとつの目安にしましょう(苦手科目のやり方は後ほど解説)
④ 「仕上がった」の基準はこれ!
■進学校を目指す人
意気込みとしては……
「全問正解して、友だちに説明できるレベル」
が理想の基準です。
-
“たまたま正解”はまだNG
-
解説を見たらわかる、もまだNG
-
自分の力で、初見で、説明できるか?が大事
公立高校の入試は標準問題が中心。
だからこそ、ミスなく得点できる力が必要です。
■苦手科目・苦手分野がある人
苦手分野はまず
A問題(基本問題)を全範囲で完璧に
これだけで
平均点・上位3割のラインに近づきます。
B問題で悩むものは、今は無理にやらなくてOK。
まずはA問題を鉄板にしましょう。
⑤ 後半の“実践問題”は秋から本領発揮
夏〜秋にかけて、
-
前半(単元別)
-
後半(実践問題)
の両方を“ぐるぐる回す”時期に入ります。
前半の「単元別」を復習することで
基礎の確認・定着、記憶の抜けを防げます。
後半の「実践問題」で
初めて見る問題への対処、応用力を養えます。
実践問題は
過去問と併用すると効果が出ます。
ただし、どの問題も“やりっぱなし”は絶対にNG。
必ず復習して定着させましょう。
⑥ 伸び悩んだら、迷わず基本に戻る
「最近伸びない…」と感じたら、
たいていは基本が抜けているパターンです。
-
A問題を丁寧にやる
-
解説を読み込む
-
「友だちに説明できるか?」を基準にする
この“基本への回帰”が一番伸びます。
⑦ 直前期は「まとめ」「一問一答」が武器になる
冬休み〜直前期は、
-
過去問(新しい問題を解くのも大事)
-
問題集のまとめページ
-
一問一答
などを繰り返します。
特に歴史の「三大改革」など、
混乱しやすい分野はここで一気に整理できます。
この問題集が受験当日まで頼れる“最後の辞書”になります。
まとめ: 「整理と対策」は“何度も繰り返す”ことで最強になる
この問題集を
- 中2冬休み~春休みに1周
- 模試ごとに解く
- 夏休みに前半の「単元別」を仕上げる
- 夏休み以降は前半(単元別)&後半(実践編)
- 直前期はまとめと仕上げ
この流れで回すと、
受験直前の不安が大きく減り、点数が安定します。
そして、やり込んだ問題集は一生もの。
大学生になったら家庭教師や塾のバイトでも役立ちますし、
将来お子さんに教えるときにも使えますよ。
高校受験の年間計画はこちらでも詳しく解説しています👇

応援しています^^ 牛込伸幸